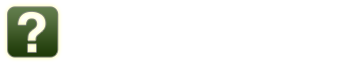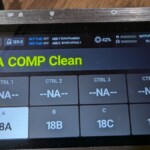1971年生まれなので人にはよく「大阪万博の次の年に生まれました」という言い方をします。
1970年の万博は自分に取ってはもはや憧れのような感情があります。
跡地である万博記念公園には子供の頃からよく遊びに行ってましたし。
万博、という物に触れたのは1990年の「花博」。
当時勤めてた会社のみんなと行ったのを覚えてますが、思い出せるのは未完成だったパキスタン館。
そして、ナムコが出展してた「ギャラクシアン3(28人同時プレイ)」をけっこうな時間並んでプレイした事。
まさかの当時の動画がyoutubeに・・・・このプレイ前のお姉さんのブリーフィング、覚えてるわ・・・
しかし、それ以外に花博で何を見たのかさっぱり覚えてません。
自分が子供の頃には「ポートピア81」ってのもあったよなあ・・・
2005年の「愛・地球博」は全く覚えてなかったりするので、結局は「地元開催」って事が重要なのかもしれません(笑)
そんな自分がとりあえず暑くなる前に、と家族で出かけてきました。

西ゲート入口
家族4人+義母の総勢5人だったので、5人分の交通費を考えるとパーク&ライドを利用したほうが楽と判断。
駐車場からゲートまではスムースに移動出来ましたが、予約時間の1時間半前に着いてしまったもんでけっこう待ちました。

建築基準の絡みで変なポーズのガンダム
今回予約が取れたパビリオンがイギリスだけだったので、とりあえずは会場ブラブラ。
中1の長男はまだ世界について興味がないみたいで、どうも今日も仕方ないから付いてきた感満載(笑)

思った以上に大きかった大屋根リング
大屋根リングの上にはとりあえず上がってみましたが、テレビで見るより巨大!
歩いて1周なんぞ死ねる・・・・というのが初見の感想。
ここで男性組と女性組は分かれて行動する事にしました。
長男の機嫌がもう限界突破しそうだったので、とりあえず休ませる&食いもんで宥める作戦に。
とりあえず二人でうどん食べて、地べたに座ってのんびりと。

ブツクサ言いながらカフェラテを飲むボン
それにしても大きくなったもんだよ。
一番最初に二人で出かけた京都競馬場を思い出す親父でありました。
あれから8年も経ったんやわね・・・
さて、喫煙者にとっては喫煙所を探さねば。
今回の万博2025は会場内は完全禁煙、しかし東ゲート外にはかなり広めの喫煙所が設置されとります。
「ここで休憩しとく」と大屋根リング下のベンチに座る長男を置いて喫煙所へ。
再入場スタンプを左手に押して一旦ゲート外へ。
もちろん再入場の際は手荷物検査あり。
水筒持参の場合は「自分でその中の物を飲んでみてくれ」というチェックまで入ります。
喫煙所の中はまさに万博って感じで集うスモーカー達もワールドワイド(笑)
きっとスタッフもここじゃないと吸えないのかな。
スマートフォンの翻訳アプリを使って会話している人達もチラホラ見かけました。

Commons館
へえ面白いな、と思ったのが会場にいくつかある「Commons」館。
パビリオンは建てないけども出展はする、といういろんな国が集まって展示をしてました。
どのコモンズ館もほとんど行列なしで入れるのが良き。
これこそ「博覧会」よね、という感じで色んな国が世界にあって頑張ってるんやなあ・・・と感動しました。
長男にとっては何がオモロいのかわからん、のはまだ仕方ない(笑)
ここで女性組と合流して予約していたイギリス館へ。
展示内容はイギリスの、というよりアストラゼネカとアストン・マーティンのPR動画であまり面白くなかった(笑)
ただ併設されたレストランは超人気で大行列でしたね。

ハンガリー民族音楽のライブ
18時から始まるって事で地べたに座って楽しみました。
初めて見たツィンバロン(ピアノの弦を直接マレットで叩くような楽器)に感動。
アンサンブル的にはブルーグラスにおけるバンジョーみたいなフレーズを奏でてました。
辺りが暗くなってくると各パビリオンにも灯りが。

スペイン館

オーストラリア館

そしてガンダム
この時間になるとあれだけ並んでた各レストランもガラガラに。
会場北側にあるリングサイドマーケットプレイスは店の外のテーブルに夜用の照明がそもそも未設置(笑)
ベトナム料理店「SAIGON」で軽く食事をした後は、みんな疲れ果ててたので帰路へ。

こんな感じの1回目の万博体験でした。
次回はもうちょっと調べてから夕方狙いで行こうかな、と思ってまっす。
なんやかんやとネガティブな報道が目立つ万博ですが、こうして世界の人達が集う口実があるだけでもエエやんね。
その翌日の晩飯・・・・・

まだ未完成だったインド館頑張れって事でインド料理を作ったのでした。
ナンを初めて自作したんですが、思った以上にうまく出来てよかった。
きっと作るメシもワールドワイドになっていく、そんな予感のEXPO2025です。